 パパ
パパ圧力鍋のレシピによく出てくる「急冷」って、知ってる?
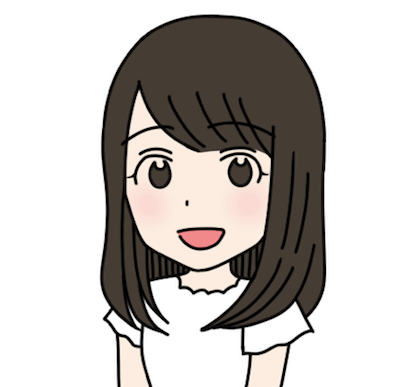
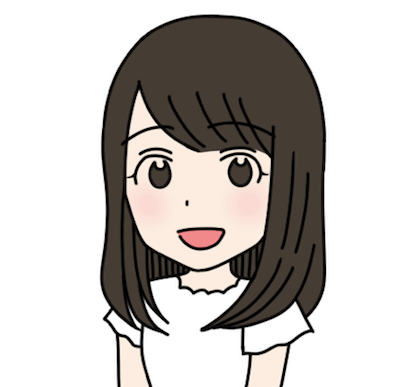
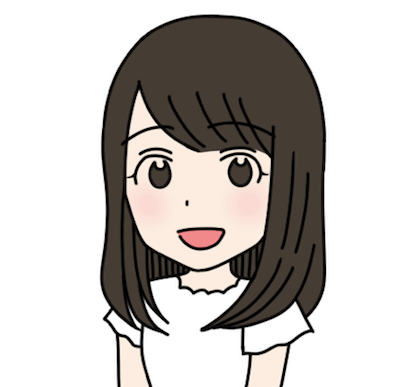
急速に冷やすってことだよね。
圧力鍋は、普通の鍋とは違う独特な使い方がありますよね。
例えば、レシピの中でしょっちゅう出くわす「急冷」という言葉。圧力鍋初心者にとっては、ちょっと手強い印象です。
具体的には、何をどうしたらいいの?急速と言っても、どの程度の早さで冷やすの?、大いに戸惑ってしまうところですよね。
今回は、圧力鍋の急冷の仕方と、どうしてそうする必要があるのかを調べてみました。
圧力鍋急冷の基本について


圧力鍋の使用を終えた後、内容物の冷却を迅速に行う方法として圧力鍋急冷が知られています。
短時間で内部の圧力を下げることができるため、料理の工程がスムーズに進むのが特徴です。
圧力鍋急冷とは
圧力鍋急冷とは、圧力鍋にかかっている高圧を速やかに解放し、内部の食品を急速に冷却する方法です。
- 調理後の圧力鍋の温度を急激に下げる
- おもりを開放して圧力を逃がす
調理時間の短縮に役立ちます。
圧力鍋急冷のメリット
圧力鍋急冷の一番のメリットは、時間節約です。
圧力鍋で高圧状態にしたあと自然に圧力を下げるのを待つ代わりに、急冷により一気に圧力を解放することで、料理の全体の所要時間を大幅に短縮できます。
加えて、急冷することで食材の色が鮮やかに保たれる効果もあります。
圧力鍋急冷の技術的側面


圧力鍋急冷はただ冷ますだけではありません。技術的な側面を探ることで、安全かつ効率的に急冷を行うことが可能です。
急冷の原理
急冷の原理は、圧力鍋内の蒸気圧を素早く下降させることにより、内部の温度を降下させることにあります。
冷水によって鍋本体を冷却することで、内部の蒸気が急速に凝縮し、圧が下がると同時に温度も下がります。
圧力鍋の構造と急冷
圧力鍋の構造は、急冷を行う際の安全を保証する重要な要素です。
急冷機能を備えた圧力鍋では、蓋のバルブを開くことで圧力を瞬時に解放できる設計になっていたり、水で冷ます際にも安全対策が施されています。
圧力調節と急冷の関係
圧力調節能力の高い圧力鍋を利用することで、より安全に急冷が可能になります。
調理中の圧力を正確に把握し、適切なタイミングで急冷を行うことが肝心。
圧力調節機能が充実していれば、料理の品質を損なわずに急冷が行えるでしょう。
圧力鍋の急冷のやり方について
ここでは、代表的な急冷のやり方を2つ紹介します。
- 水をかける
- おもりを調整する
それでは、1つずつ詳しく見てみましょう。
これからご紹介する方法は一般的な急冷の方法ですが、製品により、急冷の方法は異なります。
まずは、ご使用になっている製品の取り扱い説明書の内容をよく確認し、その手順に従うようにして下さい。
取り扱い説明書がお手元に無い場合は、メーカーに問い合わせて見ることをおススメします。
水をかける
続いて、圧力鍋に水をかけて冷やすことにより、鍋内部の圧を下げて急冷する方法です。
こちらもフィスラーの圧力鍋で、フタに水をかける急冷方法が動画で紹介されていますので、シェアしますね。
【手順】
- 鍋をコンロからシンクに運ぶ時には、傾けず、水平に保つこと。傾けると、蒸気や鍋の中身が噴き出てしまう場合がある。
- 鍋の取っ手が熱くなっている場合、直接触れると火傷の恐れがある。鍋つかみなどを着用して作業すること。
鍋のどこに水をかけるかについては製品ごとに異なりますが、フタの金属部分を指定しているメーカーが多いようです。
おもりを調整する
こちらは、おもりを使って圧力を調整するタイプの圧力鍋を急冷する方法です。
分かりやすい動画がありましたので、まずはご覧ください。
【手順】
- 急な操作や雑な操作をすると、蒸気が噴き出して火傷をする危険がある。
- 圧力低下により鍋の中の水分が再沸騰し、食材に火が通りすぎる場合がある。
- 煮汁が蒸気ともども蒸気口から排出される場合がある。
この方法で急冷する場合は、ゆっくり落ち着いて操作するようにしましょう。
また、③の対策としては、水に濡らして固くしぼったふきんを蒸気口にかぶせておき、噴き出てきたものをふき取るようにするといいでしょう。
急冷の方法を2つ紹介しましたが、おもりを操作して蒸気を排出する方法は、慣れないうちは、上手にやるのがなかなか難しそうですね。
実際、この方法を試した人達のブログなどを見ても、成功確率はあまり高くなさそうな印象があります。
トライする場合は、メーカーや製品指定の方法を確認して、それに従うことを忘れないようにしましょう。
急冷の場合に限らず、圧力鍋は、製品ごとに定められた操作手順に従わないと、思わぬ事故につながる可能性が高いです。
そうならないためにも、慎重に対応しましょう。
圧力鍋の急冷、なぜ必要なの?



急冷の方法はわかったけど、鍋が自然に冷めるのを待つのではダメなの?
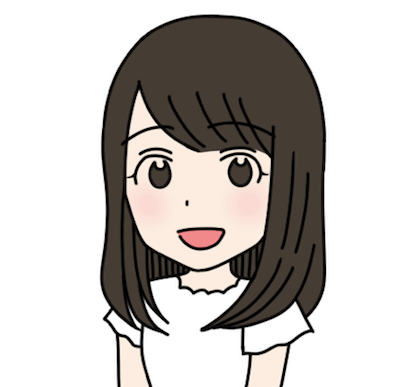
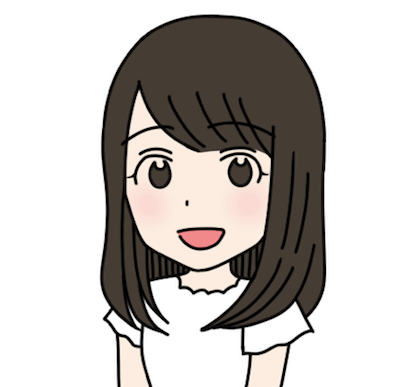
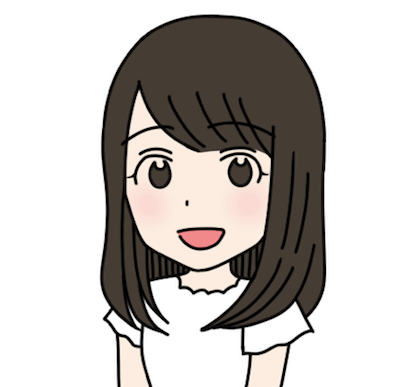
急冷するのにはちゃんと理由があるのよ。
急冷の必要を理解するために、まず、圧力鍋のスタンダードな使い方「自然冷却」について見てみましょう。
自然冷却のメリット
「自然冷却」とは、文字通り、自然に冷ますこと。
ガスの火を止めて、圧力鍋の熱が自然に収まって冷たくなるのを待つという方法です。
- 火から下ろした後、自然に冷めるのを待っている間も、鍋の中では余熱による高圧調理が続いています。
- 普通の鍋で調理する場合に比べると、使用するガスの量を節約することができます。
- そばに張り付いて火加減の調節を行う手間もいりません。
これが、圧力鍋の自然冷却という機能がもたらすメリットです。
しかし、メニューによっては、この圧力鍋のメリットが、反対に、デメリットになってしまう場合もあります。
これが、「急冷」という操作が必要になる最大の理由です。
急冷が必要になる場合
自然冷却ではなく急冷が必要になるのは、以下のようなケースが考えられます。
- 加熱のし過ぎで煮崩れしてしまう食材を使ったメニュー
- 加熱のし過ぎで味が落ちてしまう食材を使ったメニュー
- 調理の途中でフタを開ける必要があるメニュー
<加熱のし過ぎで煮崩れしてしまう食材を使ったメニュー>
加熱をし過ぎることで煮崩れしてしまうメニューで典型的なのは、肉じゃがです。
肉じゃがのお芋が煮崩れすると、煮汁にお芋のデンプンが溶け出して濁ってしまい、和風ポタージュのような、何とも微妙な味わい・食感になってしまいます。
他には、カレーやシチューのお芋の煮過ぎも、いかがなものでしょうか。
実は、私は、これが好きではありません。
自分でカレーやシチューを作るときには、鍋にお芋を最後に入れて、歯ごたえが残る程度にしか火を通さないようにしています。
カレーやシチューは、一度に大量に作って、後で温め直して食べる場合が多いですよね。
そのため、最初からお芋が柔らか過ぎると、最後に食べる頃には何も残らなくなってしまうんですよね。
<加熱のし過ぎで味が落ちてしまうメニュー>
加熱しすぎで味が落ちる食材としては、スパゲティなどのパスタ類があります。
パスタに限らず、麺類全般、熱が通り過ぎるとコシがなくなり、美味しくなくなってしまいます。
<調理の途中でフタを開ける必要があるケース>
調理の途中で食材を追加する必要がある場合です。
例えば肉じゃがなど、最初に、ニンジンなどの硬めの野菜を鍋に入れ、煮崩れしやすいお芋は、後で追加したいですよね。
このとき、途中で圧力鍋のフタを開けなくてはいけませんが、そのためには急冷する必要があります。
自然冷却が向かないメニューとして肉じゃがやパスタを例として挙げましたが、このようなメニューや食材、他にも結構たくさんありそうですよね…
そんなわけで、圧力鍋を急冷しないといけない場面と言うのは、結構多く出てきそうです。圧力鍋ホルダーとしてはできて当たり前なのかも知れませんね。
まとめ
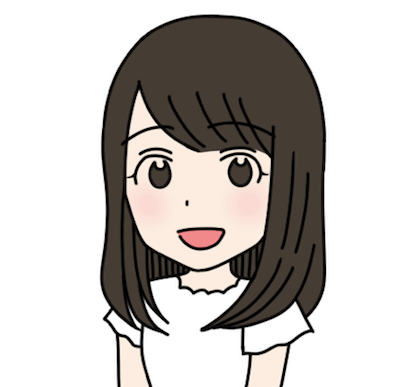
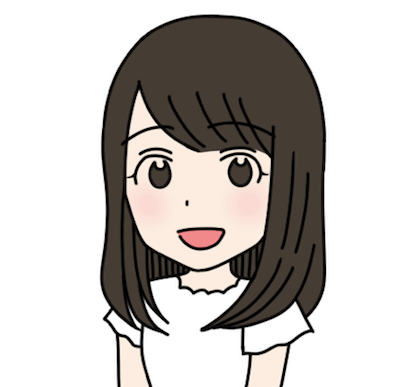
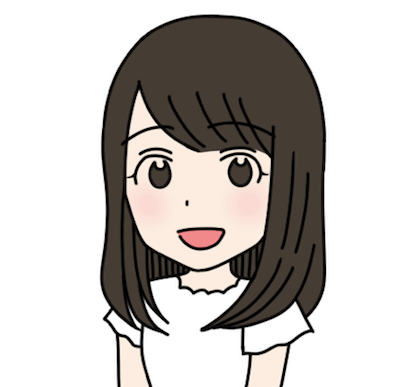
今回は、圧力鍋の急冷の方法についてお伝えしました。
圧力鍋の急冷方法は、2つです。
- おもりを調整する
- 水をかける
※ゆっくり落ち着いて作業し、中身の吹きこぼれや火傷に注意する
※自分が使用している製品の取り扱い説明書記載の手順に従う。
圧力鍋の急冷が必要な理由は、3つ。
- 加熱のし過ぎで煮崩れしてしまう食材がある
- 加熱のし過ぎで味が落ちてしまう食材がある
- 調理の途中でフタを開ける必要がある
圧力鍋、奥が深いですね。
圧力鍋を使うと、なぜ、短時間かつ手間知らずで美味しく調理できるのか。その原理を良く理解することが、圧力鍋を適切に使いこなすには必要なんだなと実感します。
上手にお料理するためには、原理を理解した上で、メニューや食材次第で様々な応用もできなければならない。
そして、長く大切に使うためには、圧力鍋の原理にしたがって、適切なお手入れをしなければならない。
全ては、原理に結び付いている感じですね。
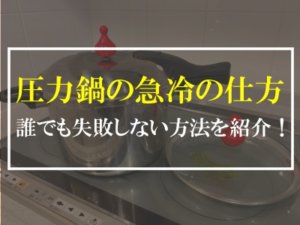
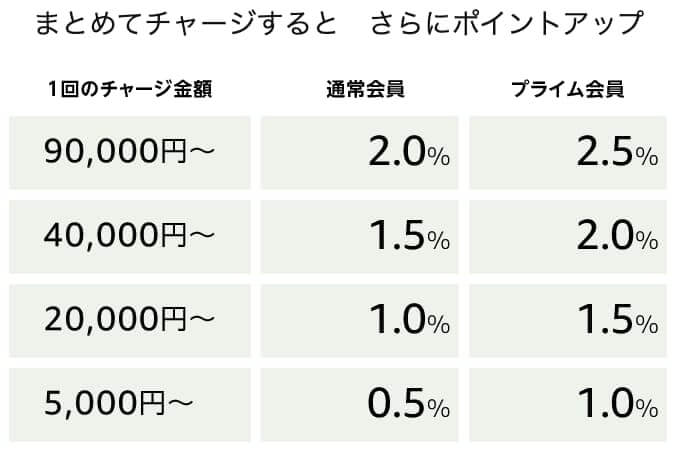

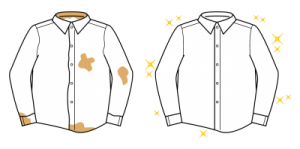
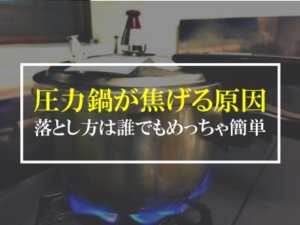
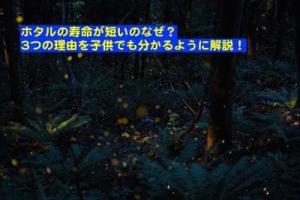


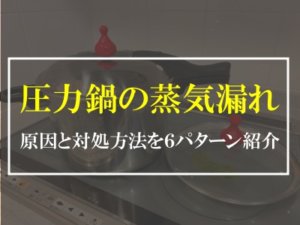

コメント